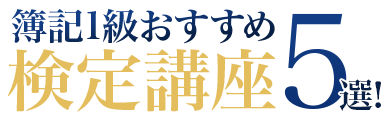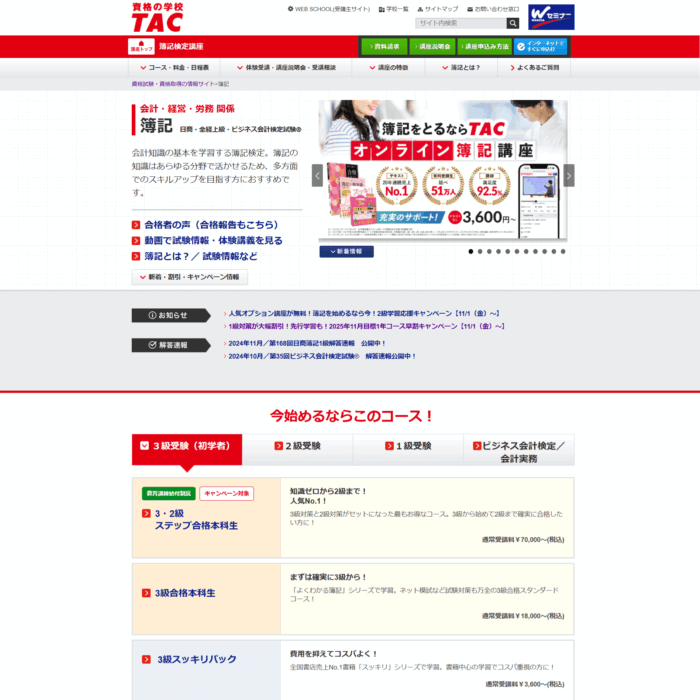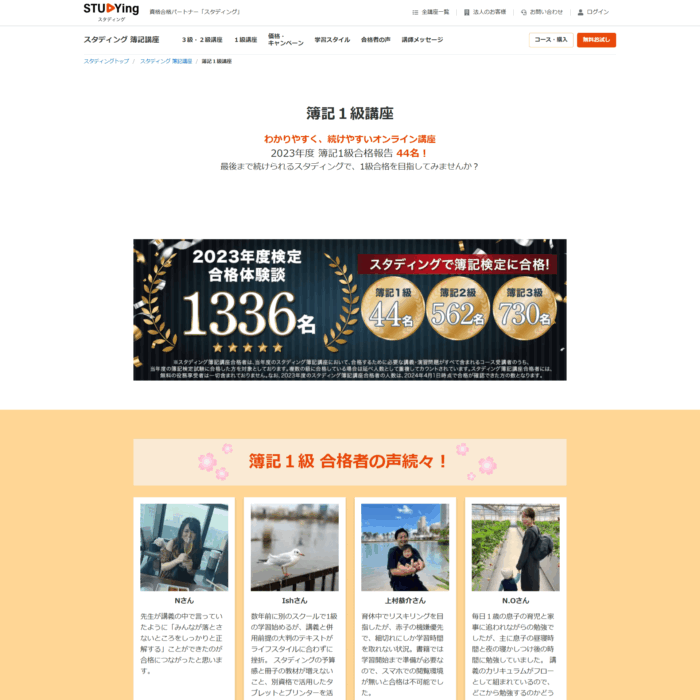簿記は就職や転職活動において、有利に働く資格です。会計事務所や経理業務につきたい方は、積極的に取得するとよいでしょう。そこで、簿記の種類を理解することが重要です。社会的評価を得られる段階であれば、アピールポイントになります。ここでは、簿記の種類や難易度を解説しているので、資格取得を検討している方は必見です。
各簿記の違いについて
簿記は日商簿記・全商簿記・全経簿記の3種類があります。それぞれ、主催団体が異なり、難易度や社会的評価も変わります。働きたい業界に応じた資格を得るために、簿記の違いを理解しましょう。
日商簿記
日本商工会議所主催の簿記です。社会スキルとして高く評価されており、1級合格者は税理士試験を受けられます。学歴や年齢に制限がないため、積極的に挑戦できます。初級・3・2・1級と分かれているので、自身のレベルに合った取得が可能です。
とくに初級は、ネット受験のため気軽に参加できます。簿記の基礎と複式簿記が試験範囲です。合格ラインは正解率70%以上ですが、受験者の50~60%が合格します。比較的、取得しやすいレベルでしょう。
また、2・3級は年に3回、指定会場で受験します。受験日に向けて、計画的な学習が必要です。3級は商業簿記が試験範囲となり、合格ラインは正解率70%とされています。合格率は40~50%なので、やや難易度が高いといえます。
さらに、2級は商業簿記と工業簿記が試験範囲です。合格ラインは正解率70%で、合格率は10~30%のため難易度は高めです。そして、1級は年に2回の受験日程になります。ほかの級よりも受験日が少ないので、仕事に活かす場合は慎重になりましょう。
商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算が試験範囲です。合格ラインは、1科目ごと正解率40%以上となります。合格率は8〜10%とされており、簿記のなかでもとくに難関です。また、各級の結果は、約1か月後に発表されます。就職や転職のタイミングに合わせて、取得を目指しましょう。
全商簿記
全国商業高等学校協会が主催団体の簿記です。受験者は商業高校の生徒がメインとなりますが、そのほかの方も受験できます。1級取得者は日商簿記2級相当になるので、就職面接ではアピールになるでしょう。
試験日程は年に2回あり、3・2・1級と分かれています。2・3級は商業簿記が試験範囲で、合格ラインは正解率70%以上です。おおよそ60~70%の合格率なので、簿記初心者に向いています。
また、1級は会計・原価計算が試験範囲です。合格ラインは正解率70%以上で、合格率は35~45%とされます。難易度は高くなるので、学習計画をしっかり立てましょう。
全経簿記
全国経理教育協会主催の簿記です。経理関係に就職する場合、とくに役に立ちます。上級に合格することで、税理士の受験資格が得られることも魅力です。日商簿記1級でも税理士を目指せますが、全経簿記上級の方が難易度は低くなります。
税理士になりたい方は注目すべき種類です。また、レベルは基礎・3・2・1・上級の5段階に分かれています。基礎から1級までは、年に4回受験が可能です。時間を効率的に使えるので、徐々にスキルアップができるでしょう。
3級は商業簿記、2級は商業簿記・工業簿記、1級は商業簿記・会計・原価計算・工業簿記が試験範囲です。基礎から1級までは、全科目70%以上の正解率で合格になります。基礎・3級は合格率70%のため、初心者におすすめです。
また、2級の合格率は商業簿記が40%・工業簿記が80%とされるので商業簿記の学習に重点をおきましょう。さらに、1級の合格率は商業簿記と会計が35%・原価計算と工業簿記が50%程度です。
全科目難易度が高くなるので、バランスよく学習をしましょう。そして、上級は年に2回の受験が可能です。試験範囲は、商業簿記・会計学 工業簿記・原価計算になります。各科目40点以上、合計280点以上が合格ラインです。合格率は20%とされるので、非常に難関であり価値があります。
難易度にも違いはあるのか
3種類の簿記は試験範囲が異なり、難易度にも大きな幅があります。合格率を高めるために、自身に最適な種類とレベルを選びましょう。ここでは、レベル別に分けて適切な簿記を紹介しています。
簿記初心者
簿記を初めて学ぶ方や学生は、全経簿記の基礎簿記会計から受験しましょう。初心者レベルであり、基礎取得の確認になります。また、次の段階では、日商簿記初級・全商簿記3級・全経簿記3級が受験の目安です。3種類の難易度は同等なので、日程や合格率を考慮して受験しましょう。
簿記上級者
上級としては、日商簿記2級・全商簿記1級・全経簿記1級が同等の難易度です。試験範囲も一致しているので、3種類同時に受けてもよいでしょう。1年間で日商簿記は3回・全商簿記は2回・全経簿記は4回受験可能です。年間9回のチャンスがあるので、難易度が高くても挑む価値があります。
簿記最上級者
日商簿記1級と全経簿記上級が、最上級者として同等のレベルです。税理士など、経理・税金のプロフェッショナルは必須となります。とくに、日商簿記1級は実務で使える内容です。就職後は、スムーズに業務を進められるでしょう。
また、税理士資格を取るには、どちらかの資格が必要です。日商簿記1級の合格率は8~10%と低く、全経簿記上級の合格率は20%とやや高くなります。そのため、税理士を目指す方は全経簿記上級の受験がおすすめです。
就職・転職に有利な簿記試験はどれ?
簿記は種類や級ごとに社会的評価が異なります。就職や転職でアピールできるレベルを目指すとよいでしょう。ここでは、面接で有利となる簿記を紹介します。
優先して取るべき簿記
一般的に日商簿記への評価が高く、広く認知されています。年間50万人が受験しており、アピールポイントとする方は多いでしょう。また、試験は実務的な内容のためスキルの説得力が出ます。企業は即戦力として期待するでしょう。就職や転職対策の場合、優先的な受験がおすすめです。
履歴書に書けるレベルとは
3種類の簿記は、各級で難易度が異なります。そのため、履歴書に記入する際は注意しましょう。社会的評価を得られる基準は、日商簿記2級以上・全商簿記と全経簿記1級以上です。これら以下は記入を控えましょう。
まとめ
簿記はさまざまな業界で通用するので、取得する価値があります。就職・転職を予定している方は、積極的に受験しましょう。また、簿記1級レベルは非常に難しいため、予備校に通うことがおすすめです。専門講座を受けることで、ほかの勉強や仕事で忙しい中でも、上手に簿記と向きあえるでしょう。また、モチベーション維持にもなるので合格率は高まります。本気で取得したい場合は、心強い存在です。ぜひ、将来のために専門講座を受けてみましょう。