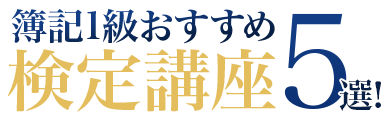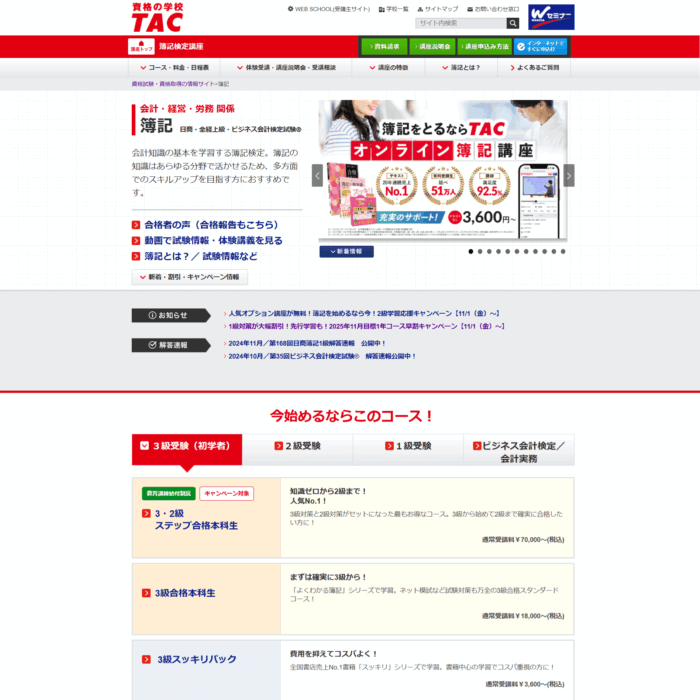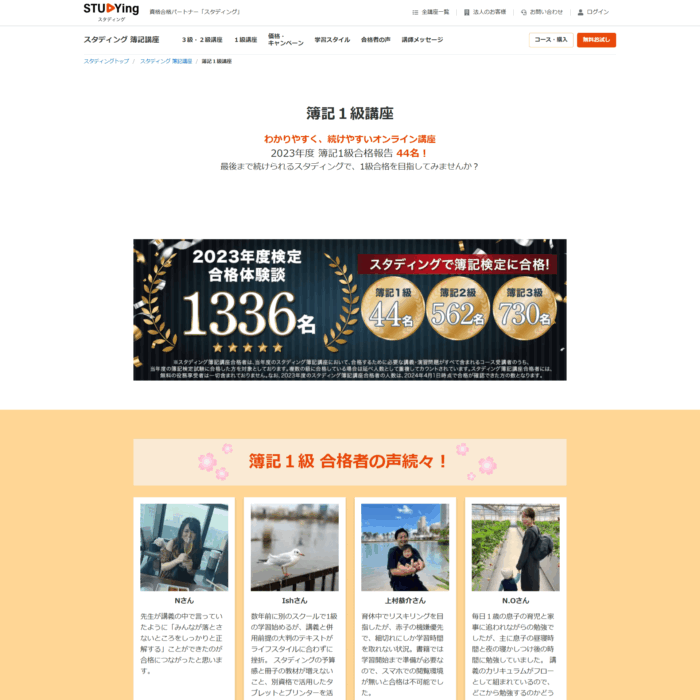簿記1級合格には、まず学習時間の確保が重要です。一般的に、簿記1級合格には500~600時間前後の勉強が必要といわれており、合格するためには、効率よく学ぶ工夫とメリハリあるスケジュール管理が欠かせません。短期間で合格を目指すには、計画的に学習し苦手を克服することが大切です。
簿記検定1級合格に必要な勉強時間は?
ここでは、簿記1級合格に至るまでの学習目安と、忙しい社会人や学生がどのようにして時間を確保すればよいかについて紹介します。
基礎の定着から応用演習までを網羅的に行うためには、多くの勉強量が求められますが、ポイントを押さえれば無理なく学べます。合格圏に到達するためには、スケジュール管理と集中力の維持が重要です。
効率よく学ぶための目安時間とスケジュールの組み方
簿記1級の学習時間は、一般的に500~600時間がひとつの目安といわれます。1日2時間ほどコンスタントに勉強できるペースなら、8~10か月程度で到達可能ですが、まとまった時間を確保できない方は土日や早朝など、空き時間に集中学習を取り入れる工夫が必要となります。
基礎固め期、応用・演習期、直前対策期に分割して学ぶのがおすすめです。たとえば前半2~3か月を基礎固めに充て、続く2~3か月で演習と理解の深掘り、そして最後の1か月ほどで総まとめと模試対策を集中的に行うといった計画が立てやすいです。
また、進捗を可視化できるツールやアプリを用いて、毎日の目標を達成したかどうかを記録すれば、学習習慣を途切れさせずに継続できます。
忙しい人が時間を確保するコツ
仕事や家事、学業と両立しながら簿記1級を目指す人にとっての課題は、勉強時間をどう確保するかです。まずスキマ時間を徹底活用しましょう。通勤中や休憩時間に携帯アプリで仕訳問題を解いたり、音声講義を聴いたりすれば、短時間でも学習効果を高められます。
さらに、帰宅後の学習時間を固定しましょう。また、週末には2~3時間程度のまとまった時間を取り、苦手分野の復習や模擬問題への取り組みに充てるのが理想的です。
2級・3級とはどのくらい難易度が違うのか
簿記3級・2級と比較して、1級がなぜ段違いと呼ばれるほど難易度が高いのかを確認していきます。出題科目の増加や内容の専門性アップにより、3級・2級までの延長では対処しきれない部分が多く存在するのが1級の特徴です。
試験範囲と出題レベルの差
簿記1級では「商業簿記」「会計学」「工業簿記」「原価計算」の4科目が出題範囲となり、2級までにはなかった会計理論や高度な原価計算が難点です。たとえば会計学では複雑な引当金の処理や連結会計の論点など、理論的背景や実務的観点からの理解が必須です。
さらに工業簿記・原価計算では、材料費や労務費の詳細な計算だけではなく、管理会計的な手法を踏まえた問題も登場します。3級は入門、2級は実務、1級は経営判断に役立つ力が求められます。
合格率の比較からわかる実情
日本商工会議所が公表するデータによると、3級の合格率は40~50%前後、2級は15~30%前後で推移しているのに対して、1級は回によって多少の変動はあるものの10%前後という数字が続いています。
そもそもの受験者数が少ないうえに、合格まで到達する層も限られているという、難易度の高さがうかがえます。ただし、合格率だけを見てあきらめる必要はありません。
1級の受験生はすでに3級や2級を乗り越えてきた人が多く、基礎力が身についているため、ポイントを押さえた学習計画や教材選びを行えば合格が可能です。
簿記検定1級の対策ポイント
出題範囲が多岐にわたるため、苦手分野を放置してしまうと合格点に届きづらいのが簿記1級の特徴です。合格に近づくためには幅広く・かつ深く学ぶことが必要です。問題演習や時短テクニックを取り入れて実践力を磨くことが重要になります。
合格者の多くが実践した学習方法
簿記1級は単なる暗記だけでは範囲に圧倒され挫折しがちです。まず基本を理解し、定期的に演習を繰り返しましょう。たとえば、会計学の複雑な理論を学ぶときは、条文や基準の趣旨を大まかに把握し、その後実際の仕訳や計算問題に当てはめてイメージを固めるという手順が効果的です。
工業簿記・原価計算でも、基本となる個別原価計算や標準原価計算を何度も演習し、コストや管理会計に関する苦手部分をなくすことが重要です。
苦手科目を克服するためのアプローチ
簿記1級では、各科目で最低40%以上の得点がなければ合格ラインを超えていても不合格になるルールがあります。そのため、どこかひとつでも大きく苦手意識を持っている科目があると、合計点で70%を確保していても足切りになるリスクが高いです。
まず苦手な部分を洗い出して要因を分析しましょう。たとえば工業簿記であれば減損や標準原価計算の理論が理解できていないなど、具体的にどこで躓いているかを明確にすることが重要です。
そのうえで、類題を解き、わからない部分は参考書で補いましょう。最初はスピードよりも正確性を重視し、徐々に処理の型を覚えて解答時間を短縮していけば、苦手分野も合格点に乗せられる可能性が高まります。
まとめ
簿記1級は決して簡単な試験ではありませんが、それだけに得られるメリットは大きく、キャリアアップや会計知識の総合力向上に直結します。とくに500~600時間程度の学習が必要とされるため、日々の時間確保と集中力の維持が合否を左右します。2級・3級とは出題範囲もレベルも格段に違いますが、これまで学んできた基礎を上手に活かし、苦手科目を早めに克服する戦略を立てましょう。